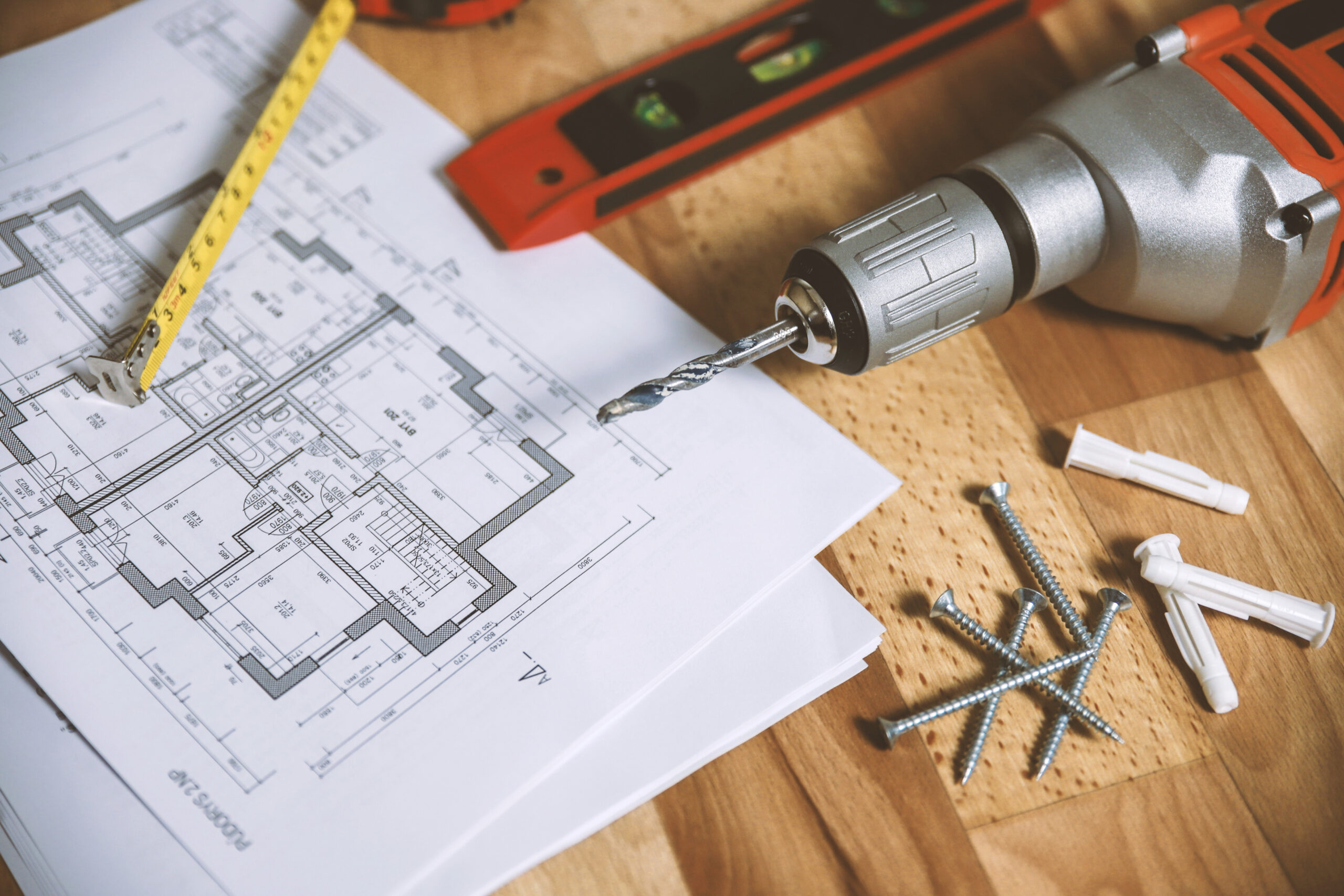図面には「線」がたくさん使われていますが、それぞれに意味やルールがあることをご存じですか?
たとえば、実線と破線ではまったく違う情報を示していますし、線の太さや種類が違うだけで読み取り方が変わってしまうこともあります。
このブログでは、建築図面や機械図面で使われる「線の種類」について、初心者でもわかるように丁寧に解説していきます。
これを読めば、「この線、何を表してるの?」という疑問が解消され、図面を読む力がぐっとアップするはずです。
実線:最も基本となる線
図面で最もよく見かけるのが「実線」です。これは対象物の輪郭や、見えている部分を表す線であり、図面の中でも最も重要な役割を持っています。
実線にはさらに種類があり、線の太さや間隔で使い分けられています。
- 太い実線:主に「外形線」や「見えがかりの形状」を示す
- 細い実線:寸法補助線、引出線、寸法線などに使用される
特に建築図面では、柱や壁、床などの見える部分に太い実線が使われており、パッと見ただけでも形状がわかるようになっています。
破線:見えない部分を表す線
破線(点線)は、目には見えない部分や、裏に隠れている構造物を示すときに使われます。
たとえば、天井裏に隠れている梁や、床下にある配管などが該当します。機械図面では、部品の内部構造や、他の部品の裏側にある形状を示すのにも使用されます。
- 細い破線:主に「隠れ線」として使われる
- 太い破線:特殊な用途(たとえば建築の仮設構造など)で使う場合もある
破線を見落とすと、構造の理解や施工にミスが出る可能性があるため、要注意です。
一点鎖線:中心線や対称軸を示す線
「一点鎖線」は、点と長い線が交互に連なった線です。これは主に、円や円弧の中心、対称性を持つ構造の軸を示すために使われます。
使用例:
- 円柱や円筒の中心線
- 左右対称の構造の対称軸
- 配管の中心軸
また、この線は寸法の基準になることも多いため、寸法線と組み合わせて使用されることもよくあります。
二点鎖線:移動や繰返し部分を示す線
二点鎖線(短い線・点・短い線)は、可動部分の範囲や、繰り返される構造を示すために使われる線です。
例としては、以下のような場面で使われます。
- 扉や引き出しの開閉範囲
- 回転部品の回転軌跡
- 展開図や詳細図の展開範囲
図面によっては、二点鎖線に補助文字を添えて、動きの方向や構造の説明を付け加えることもあります。
波線・ジグザグ線:省略や切断を示す線
「波線」や「ジグザグ線」は、一部を省略して表すときや、断面図で切断位置を示す場合に使われます。
特に以下のようなシーンで登場します。
- 長い配管の一部を省略する
- 柱や梁などの一部だけ断面を示す
- 詳細図で一部を拡大表示するための区切り
このような線は、図面上のスペースを節約しながらも、必要な情報を正確に伝える役割を果たしています。
寸法線・補助線・引出線の違い
図面で寸法を記載する際には、以下のような線が使われます。
- 寸法線(細い実線・両端に矢印):長さや角度などの寸法値を記載するための線
- 補助線(細い実線):寸法を測る起点・終点を指し示す線
- 引出線(細い実線):注記や部品名などを図面上に示す際に使う線
これらの線は細かいですが、正確な情報伝達には不可欠な存在です。初心者のうちは混同しやすいので、図面を読みながら慣れていくことが大切です。
色や線の太さによる区別について
最近のCAD図面では、線の色や太さによって情報の階層が表現されていることも多くあります。たとえば:
- 赤:電気系統
- 青:給排水系統
- 緑:構造系統
- 黒:仕上げや建築の構造
ただし、これは企業や設計者によって異なるルールが設定されている場合があるため、凡例(レジェンド)や図面の注釈を確認することが重要です。
線の種類を正しく理解するメリット
線の種類を正しく理解すると、以下のようなメリットがあります。
- 施工ミスを防げる:破線や中心線を見落とすと、施工時の寸法ミスや加工ミスに直結するため
- 図面間の整合性が保てる:平面図・断面図・詳細図の関係が明確になる
- スムーズなコミュニケーションが可能:設計者・施工者・製造者の間で誤解が減る
図面は「線」で情報を伝える、いわば言語のようなもの。言葉を学ぶように、線の使い方を覚えることで「読み書き」が可能になります。
まとめ:図面の「線」を読む力をつけよう
図面に使われる線には、それぞれ明確なルールと意味があります。
設計や建築、製造の現場では、それを正しく読み取る力が求められます。
初心者のうちは、
- 実線=見えている部分
- 破線=隠れている部分
- 一点鎖線=中心や対称
- 二点鎖線=可動や展開
といった基本のルールを頭に入れておくだけでも、図面がぐっと読みやすくなります。
今後、設計図や施工図に触れる機会がある方は、ぜひ線の種類に注目してみてください。
図面の「言葉」が読めるようになると、ものづくりの世界がもっと楽しくなりますよ。