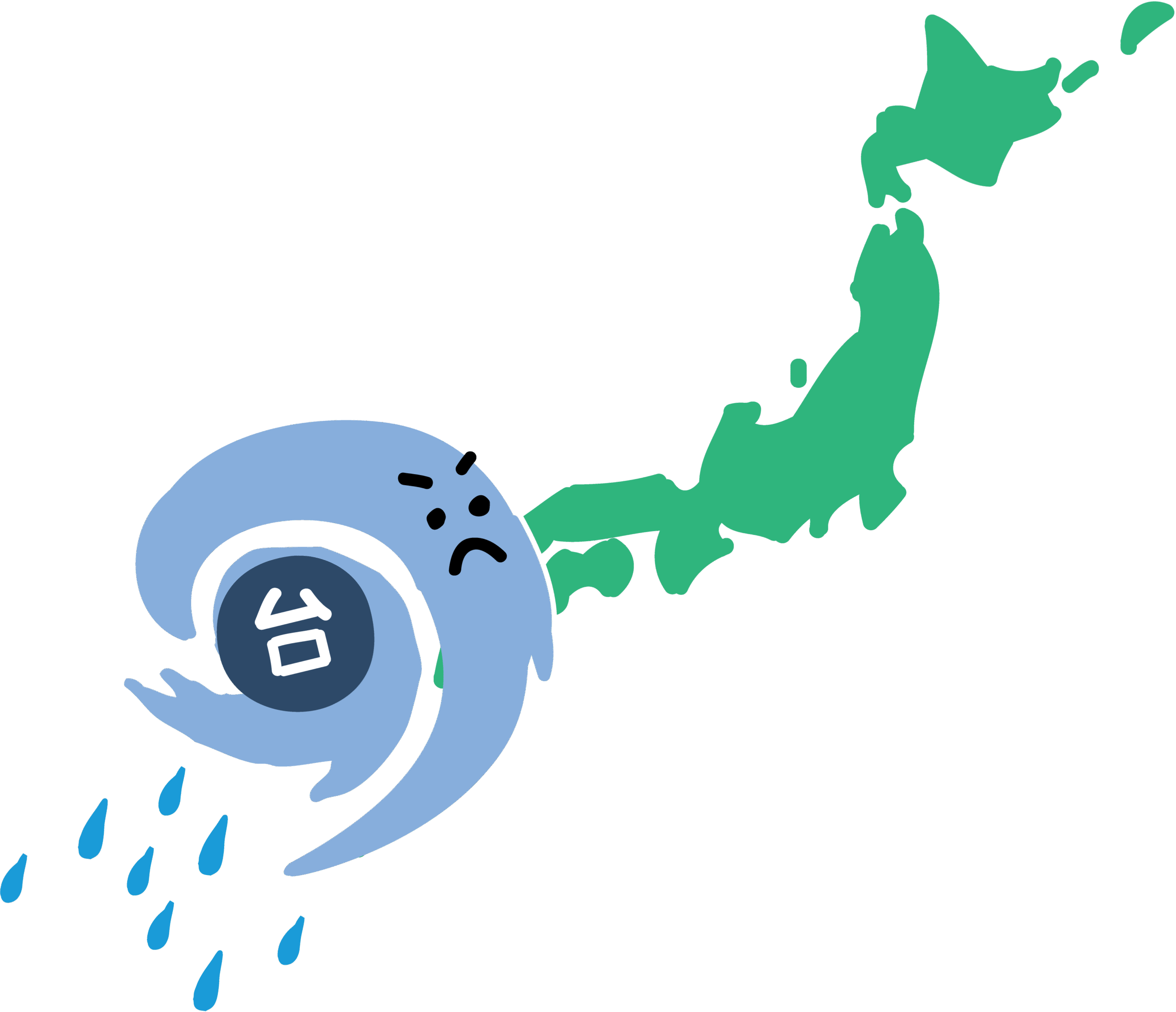毎年、夏から秋にかけて耳にする「台風」のニュース。旅行やレジャーの計画、農作業、防災準備など、台風が来やすい時期を知っておくことは非常に重要です。では、実際に「台風はいつ多いのか?」という疑問に対して、発生数、接近・上陸の統計やその背景、過去の事例、そして備え方までを総合的に見てみましょう。本記事では、気象庁や関連データをもとに、月別傾向と注意点をわかりやすく解説します。
台風とは何か? 基本のおさらい
まず、台風とは熱帯低気圧が発達したもので、一定の基準(最大風速など)を満たして「台風(Typhoon)」と呼ばれるものです。
発生地域は主に熱帯・亜熱帯の海域で、周囲との気圧差や海面水温、上空の風の条件などが重なると強化されます。
日本に影響を及ぼす台風は、太平洋側で発生し、西または北西方向に進みながら進路を変えるものが多く、そのうち一部が日本列島に近づいたり上陸したりします。
台風の動きには「スピード」「進路の曲がり方」「接近前の余裕時間」なども重要で、同じ時期であっても被害には大きく差が出ることがあります。
台風の年間発生数・接近・上陸の統計傾向
日本やその周辺で記録されている統計データから、台風の年間傾向を見てみましょう。
- 1991年~2020年の30年平均では、年間約 25個 の台風が発生するとされています。
- そのうち日本列島に「接近する」台風は約 11~12個、実際に「上陸する」ものは平均で 3個前後 と言われます。
- 月別で見ると、発生数・接近数・上陸数とも、8~9月が最も多い傾向があります。
具体的には、以下のような月別の平年値があります(発生/接近/上陸):
| 月 | 発生数 | 接近数 | 上陸数 |
|---|---|---|---|
| 7月 | 約 3.7 | 約 2.1 | 約 0.6 |
| 8月 | 約 5.7 | 約 3.3 | 約 0.9 |
| 9月 | 約 5.0 | 約 3.3 | 約 1.0 |
| 10月 | 約 3.4 | 約 1.7 | 約 0.3 |
このように、7〜10月にかけて台風関連の数値が大きくなることが統計上明らかです。
また、例年では 8月が発生数でピーク、9月が上陸数で最も多い月 という傾向もあります。
ただし、台風は1年を通じて発生する可能性があり、冬期や早春にも発生例があることも、統計上確認されています。
なぜ 8〜9月に台風が多くなるのか? 気象的背景
なぜ台風は特定の時期に集中するのか、その仕組みを見てみましょう。
- 海面水温の高さ
夏の終わり頃は太平洋や南シナ海の海面水温が高く、熱エネルギーを得やすいため、台風の発生・発達が起こりやすくなります。 - 上空の風の条件(風切変化など)
発生海域から日本に進む途中、強すぎる風や風向変化があると台風が崩れやすくなります。しかし、8〜9月では風切変化が比較的少ない条件になることが多く、台風が勢いを維持しやすいのです。 - 太平洋高気圧・偏西風の影響
夏季は太平洋高気圧が張り出しており、台風がその縁を回るように進む傾向があります。晩夏から秋にかけて太平洋高気圧の勢力が弱まり、台風が日本方面に曲がりやすくなるルートが形成されやすくなります。 - 梅雨明け・前線の影響
梅雨が明け、対流活動が活発化すると熱帯低気圧の初期発生が増え、それが台風に成長するケースが増えます。また、秋の前線(秋雨前線)が活発化すると、台風と連動して大雨を引き起こしやすくなります。
このように、海面水温・大気の流れ・高気圧・前線といった複数の条件が重なって、8〜9月に台風が集中する構図が成り立っています。
実際の過去事例:記憶に残る “9月の大台風”
歴史的に甚大な被害を出した台風を見ておくと、時期の危険性が実感できます。
- 伊勢湾台風(台風ヴェラ / 1959年)
9月に上陸し、名古屋湾沿岸を中心に甚大な被害をもたらしました。死亡者数は 4,697人、負傷者 32,285人とされ、日本の戦後最大級の風水害の一つです。 - 室戸台風 / 枕崎台風 / 枕崎型大型台風
これらも9月や10月に日本列島に接近・上陸した例が多く、特に東海・四国・九州地方での被害が強く残っています(例:1958年の狩野川台風=枕崎台風)
こうした事例は、9月という時期の怖さを示す実証とも言えます。
地域別の傾向:どこに台風が多く来るか
発生や接近の月別傾向だけでなく、地域別の傾向も押さえておくと実用性が増します。
- 九州・四国・南西諸島
日本の南方・西方海上に位置するこれらの地域は、最初に台風に直撃されやすい地域です。特に南から接近する台風は九州や沖縄に最初に影響を与えることが多いです。 - 本州中南部(近畿・東海・中部・関東南部)
南海上から進んできた台風が内陸に向かって進む際、このあたりを通るケースがしばしばあります。 - 東北・北海道地方
台風が上北上して、衰弱しつつ影響を与えることがあります。ただし、上陸自体は少ない傾向です。
地域によって「最も警戒すべき時期」が微妙に異なることがあります。例えば、南西諸島では早めの時期から影響を受けやすく、本州などでは 8〜9月の進路曲がりが影響を与えやすいなどの差異が見られます。
2025年の傾向と予測(最新情報)
最近の予報データから、2025年の傾向もチェックしておきましょう。
- 日本気象協会などのモデルでは、2025年の台風発生数は 6月~10月までほぼ平年並み との見通しが出ています。
- ただし、日本列島への接近数 は、8月以降 平年並み〜多め になるとの予測もあります。
- また、2025年は台風が発生してから日本に接近するまでの時間が短くなる可能性が指摘されており、対応の時間的余裕が減るかもしれません。
こうした予測も踏まえながら、夏〜秋にかけての防災意識を高めておきたいところです。
台風多発期に備えるためのポイント
最後に、台風が多い時期を見越して備えておきたいポイントをいくつか挙げておきます。
- 早めの情報確認
気象庁・地方気象台、自治体の防災情報、テレビ・ラジオなどをこまめにチェック。特に台風の進路や強さ、接近時間の更新を追うことが重要です。 - 生活・インフラ備え
雨戸・窓の補強、排水口・側溝の掃除、飛散物の片付け、土のうや排水ポンプの準備など、物理的な備えをしておくこと。 - 避難計画の確立
地域の指定避難場所、避難ルートを把握・確認しておく。家族間で連絡手段や避難タイミングを話し合っておきましょう。 - 備蓄と非常用品
食料・水、携帯トイレ・簡易トイレ、懐中電灯・乾電池、ラジオ、医薬品、予備の衣類などを前もって準備。 - 旅行・外出計画に配慮
特に 8〜9月に旅行を計画する場合は、台風シーズンを外す、または予備日を設けるなどの工夫が望ましいです。 - 住まい・建物の事前点検
屋根・瓦、雨どい・樋、外壁、配管など、老朽化や劣化しやすい部分を点検・補修しておくことが安心につながります。